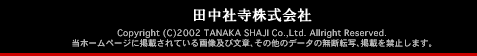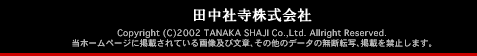|
中世建築の端正なたたずまいを今に伝える彦部家主屋。
柱や梁が描く優雅な曲線美を鮮やかに復元。 |
|
| ▲改修後写真 |
|
 |
| ▲改修前写真 |
|
 |
 |
| 彦部家の遠祖は天武天皇の皇子高市親王まで遡り、承和11年(844)に高階姓を賜り臣下した(『高階朝臣彦部家家譜』)と伝えられ、高市親王から平成11年の修理当時の現当主まで48代、永禄4年(1561)桐生に定住してから16代を数える旧家です。屋敷地は手臼山麓の高台を利用して東西約130m、南北約100mの方形の土塁と濠をめぐらせた一角と、その周辺の田地・山林を含む規模となっています。主屋は寛永年間(1630年頃)に建てられたと考えられ、裄行約19m・梁間約11mの主屋(土間、囲炉裏のある広間、オモテザシキ、オクザシキ、ウラザシキ、ナンド)と、その土間に接して明治期に建てられた裄行約17m、梁間約8.5mの突出部(染色用窯、風呂場などを備えた開放空間)で構成されています。平成4年に国の重要文化財に指定されました。 |
|
|
 |
 |
| 建物の破損状況は、軸部が内法間で最大15cm東面に傾斜し、沈下も東側柱筋で30cm以上実測されたほか、蟻害や壁面の剥落・亀裂、茅葺屋根の押釘竹の露出など著しいものでした。今回は、南面、東面、オクザシキ西面に巡る桟瓦葺の庇を撤去し、側廻りを復旧または整備(茅下ろしの下屋)、トオリドマやダイドコなど各室境に入る後設の間仕切、ハタヤの板床を撤去して一連の土間を現す…などの修理整備がなされました。彦部家は文化財として一般に公開されているため、土壁はできるかぎり在来の工法を残すようにし、耐震補強は見学者の目の届かない部分に施されました。これにより水平剛性と耐力の増大が図られました。 |
|
| |