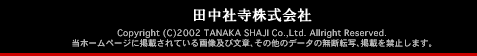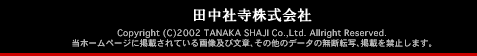|
| ▲改修後写真 |
 |
 |
 |
| 大分県北部、中津市の南東部に鎮座する薦神社は承和年間(834~48)の草創と伝えられ、社殿の西に広がる5ヘクタール余の三角池をご神体とし、池が内宮、社殿が外宮と称されています。草創時より宇佐神宮との関係が深く、宇佐行幸会で神輿に納める霊代の枕は、三角池に自生する真薦で作るならわしでした。神門は元和7~8年(1621~22)の墨書を有し、中津城主細川忠興の造営と認められます。他に類をみない形式の三間一戸二重門で、細部の絵様や彫刻も優れ、江戸時代初期の門として九州地方を代表する建築物であることから、昭和63年に国の重要文化財として指定されました。 |
|
古木の繁る社叢に守られた厳粛な神域を今に伝える古社。その東に建つ神門が、色鮮やかに甦りました。
|
|